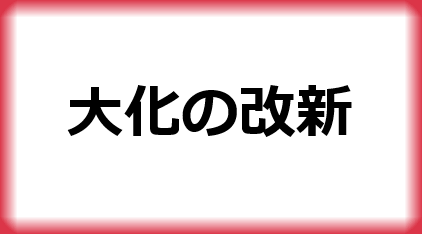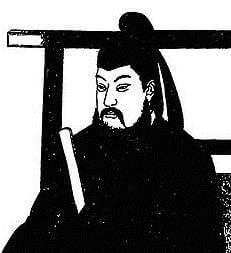中臣鎌足(なかとみのかまたり)といえば、だれでも名前くらいは聞いたことがあるでしょう。
超有名人ですが、何をしてどんな人だったのでしょうか。
今回、中臣鎌足のカンタンな経歴や、渡来人説、ミイラの場所や、子孫が現在まで続いているのかを紹介していきますよ。
中臣鎌足(なかとみのかまたり)

出身地:大和(奈良県)
生誕:614年
死没:669年10月16日
享年:56歳
時代:飛鳥時代
中臣鎌足って何した人?
中臣鎌足は、中大兄皇子をたすけて「大化の改新」を進めたお人です。
日本の未来を心配して、中大兄皇子と蘇我氏を倒しました。
ここでは、中臣鎌足のカンタンな経歴を紹介していきますよ。
中臣鎌足、経歴
中臣鎌足は、中大兄皇子(天智天皇)の部下であり戦友、そして親友です。
当時、聖徳太子が死んだ後、蘇我蝦夷(そがのえみし)という男は、舒明天皇(じょめい天皇)を天皇の位につかせました。
そして、蘇我蝦夷は、政治の実権をにぎるようになります。
さらに蘇我蝦夷の息子・蘇我入鹿(そがのいるか)は、聖徳太子の一族をほろぼして、まるで自分が天皇のようにふるまいはじめました
日本の政治は蘇我氏の思うままに動かされていたのです。
「このままでは、日本の将来がヤバイ…。」
役人であった中臣鎌足は、12歳年下の、「若いが気合が入っている」と評判だった、中大兄皇子に近づきました。
同じように日本の将来を心配していた中大兄皇子とは、すぐに気持ちが通じ仲良くなりました。
ふたりは蘇我氏を倒すことを誓い、ひそかに作戦を立てました。
そして645年、ふたりは皇居の中で蘇我入鹿を殺害し、蘇我氏を力ずくでほろぼすことに成功したのです(乙巳の変)。
その後の政治の面(大化の改新)でも、鎌足は中心となって活躍しました。
近江(滋賀県)に新しい都をつくったことも、全国の戸籍「庚午年籍(こうごねんじゃく)」の作成も、鎌足の働きが大きかったのです。
鎌足は改革に反発する勢力をうまくなだめて、中大兄皇子をたすけました。
病に倒れた鎌足の死の直前、天智天皇となっていた中大兄皇子は鎌足を見舞い、これまでの働きに対して、最高の位である「大職冠」と「藤原」の姓を、鎌足にあたえました。
のちの平安時代、権力をふるうようになる藤原氏は鎌足の子孫なのです。
こちらの記事で、大化の改新、蘇我入鹿、中大兄皇子をカンタンにわかり易く紹介しています。
>>>蘇我入鹿を5分で!ガチで聖徳太子と同一人物?中大兄皇子に暗殺された理由?
>>>中大兄皇子(天智天皇)を5分で!中臣鎌足との関係、大化の改新って?
渡来人ってほんと?
中臣鎌足が渡来人説について。
渡来人とは、中国大陸、朝鮮半島から、日本に渡ってきた人のことをいいます。
「中臣鎌足」の「足」の文字が、中国の百済(くだら)の系統ではないかという説があります。
可能性は皆無ではありません。
鎌足は実に仏教に熱心だったのです。
子息を僧にするために大陸に送っています。仏教は大陸の宗教です。
もっとも、日本人の多くは異民族の血をひいています。陸路でやってきたという説と、船に乗ってやってきたという説があります。
現在でも、中臣鎌足がどこからやってきたのか、はっきりとはわかっていないのです。
ミイラがどこかの古墳にある?
中臣鎌足のミイラがあるという話について。
中臣鎌足のお墓もしくは遺体と言われるものは、複数あるのです。
そのひとつが大阪の、阿武山古墳(あぶやまこふん)。
この古墳のミイラが、中臣鎌足ではないかという説が有力です。
腰椎、腰の骨を折っていますが鎌足が亡くなる直前馬から落ちていました。
あと、決め手は、彼以外は所有していないはずの「大織冠」が一緒に納められていたのです。
これが完全な決め手でした。
しかし、別人だという説もあります。
そのミイラは、中臣鎌足の子孫だという説もあるのです。
中臣鎌足の子孫・・・。一体血をひく人が何人いることやら。
現代でも名字が藤原の人は、中臣鎌足の子孫の可能性があります。
ただし、あちこちの豪族が箔をつけるために藤原姓を名乗ったいきさつがありますので、すべてだということはありません。
まあ、大阪の阿武山古墳(あぶやまこふん)に眠っているのは、中臣鎌足だと言っていいのではないでしょうか。
子孫といえば、タレントの中川翔子さんが子孫なんだそうですよ。
中大兄皇子との関係、出会いが素敵?
中臣鎌足と中大兄皇子(なかのおおえのおうじ)は、戦友であり、親友ですね。
そのなれそめが、ちょっと素敵です。
中臣鎌足は、蘇我氏を倒すためには、中大兄皇子が必要と考え、なんとか仲良くなりたかったのです。
もともと、皇子である中大兄皇子と、一役人である中臣鎌足は、身分がぜんぜん違うため、話すチャンスなんてないのですね。
出会いは、中大兄皇子が「けまり」をしていた時。
中大兄皇子の履物が、スポーンと飛んでいったのです。
そこにいた鎌足が拾って、丁寧に差し出したとき、「チャンス!」と思った中臣鎌足は話しかけます。
中大兄皇子も「蘇我氏のせいで日本がヤバイ。」と考えていたので、自然と仲良くなります。
その後、学問の面などで、で交流を深めていきます。
ふたりの身分を超えた友情は、一生ものとなりました。
鎌足は、つねに中大兄皇子の役に立つことを考えます。
男同士ですが、花を送り合うなどのこともしていたようです。当時はそういう習いがあったそうです。
これは男色とかではなくて、友情としてです。
中大兄皇子にとっても、鎌足は本当にとくべつな存在でした。
天智天皇(中大兄皇子)がめっちゃ気に入っていた美人がいました。
この美人は、ただの使用人ではなく、側室にするレベルに気に入っていたそうです。
こういう女性を采女(うねめ)といいますね。
天皇の采女なんて、本当はだれもが指一本触れられない相手です。
でも、鎌足が彼女が好きだと知った天智天皇は、「おまえなら。」とスッと彼女を与えます。
また、病に倒れた中臣鎌足を、天智天皇(中大兄皇子)がお見舞いに行ったとき。
中臣鎌足に、最高の位である「大織冠(だいしょくかん)」と、「藤原」の姓をあたえました。
この次の日、中臣鎌足は亡くなります。
のちの平安時代、権力をふるうようになる「藤原氏」は、中臣鎌足の子孫ですね。
このように、ふたりは身分を超えた、親友だったのです。
こちらの記事で、中大兄皇子(なかのおおえのおうじ)について、カンタンにわかり易く紹介しています
>>>中大兄皇子(天智天皇)を5分で!中臣鎌足との関係、大化の改新って?
まとめ
中臣鎌足のミイラの場所について、渡来人説について、そして子孫は現代まで続いているのかについて紹介しました。
今回の疑問の答えは、すべて信ぴょう性がありそうで、なんだかスッキリです。でもしょこたんが
中臣鎌足の子孫だなんてビックリですね。
ということで、中臣鎌足をカンタンに語るポイントは、
・中大兄皇子といっしょに、蘇我氏をほろぼした
・中大兄皇子とめっちゃ仲良し
・のちの平安時代の権力者「藤原」の姓は中臣鎌足の子孫
・しょこたん(中川翔子)が中臣鎌足の子孫
最後まで読んでいただきありがとうございます^^